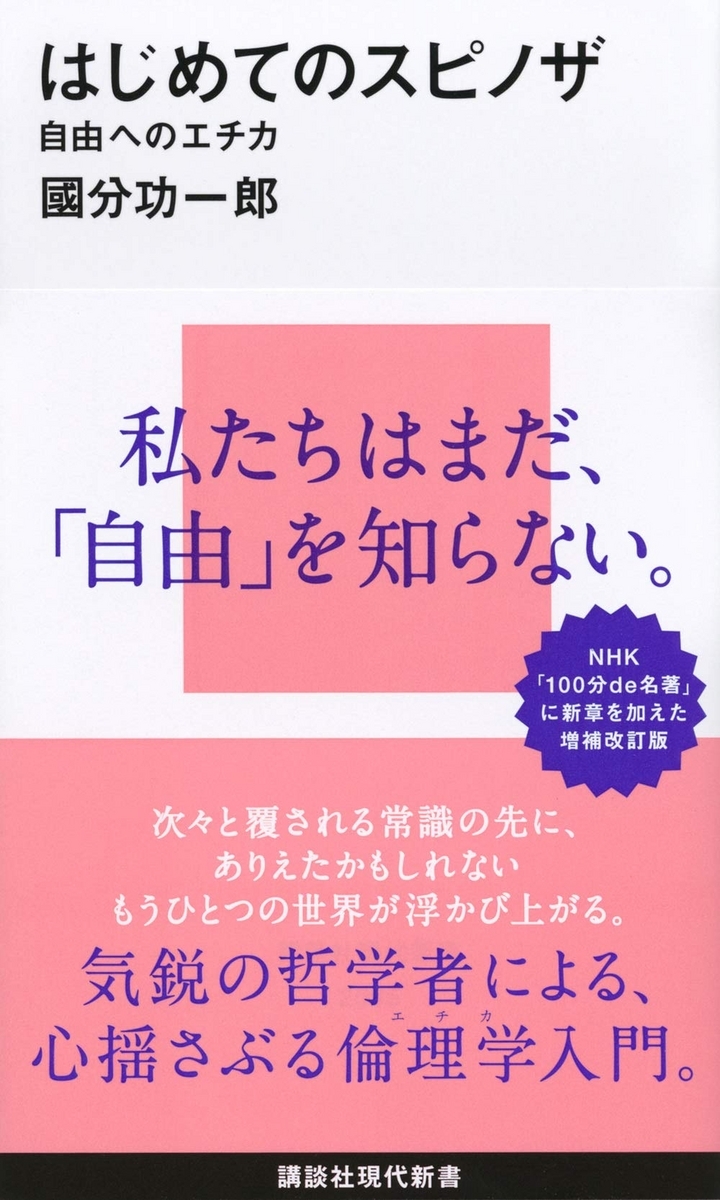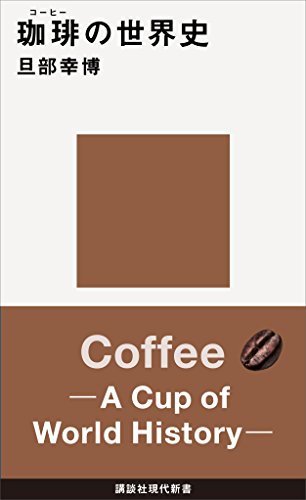アニメのキャラクターがどれもだいたい同じに見えてきた…などと言おうものなら、アニメファンに「それはお前の見る目の問題だ」「加齢によって細かい差異が見分けられなくなったのだ」とか怒られることだろう。実際そうかもしれない。
しかしそれでも…ハッキリと「違う」デザインのキャラクターが主役の日本アニメが現れた時は、明白な「新しさ」を感じさせてくれるのだから、やはりキャラ造形のフレッシュさを常に追求していくことはアニメにとって大事なのではないか。映画『金の国 水の国』の話である。
『金の国 水の国』鑑賞。仲の悪い二国の男女が出会い恋に落ちる、良くも悪くも古典的・童話的な物語だが、ファンタジックな中東イメージの豪華絢爛な美術と、日本アニメでほぼ見かけないキャラ造形がフレッシュで楽しめた。資源を巡る戦争を食い止める話として見ると意外なほど現代に刺さってる感も。 pic.twitter.com/91lL47KtPF
— ぬまがさワタリ (@numagasa) 2023年1月30日
というわけで『金の国 水の国』の感想をまとめておく。今週はおじさん同士が愛し合うドラマとか、おじさん同士が憎み合う映画とかで忙しかったので(どんな週だよ)、鑑賞から少し間が空いてしまったが、おかげで原作漫画を読んだりもできた。アニメ版も良かったが、個人的には漫画の雰囲気がより好みであった。詳しくは後述。
『金の国 水の国』原作→https://amzn.to/3IflIww
そんなネタバレ云々みたいな物語ではないと思うが、特にネタバレは気にしないので一応注意。
【ざっくりあらすじ】
時は大昔、舞台はファンタジーな古典童話っぽい世界…。隣り合う二つの国がいがみあっていたが、ひょんなことから両国の男女が出会い恋に落ちる。おっとりした姫サーラと、口の達者な青年ナランバヤルは、政争に巻き込まれたりしながら、二つの国の国交を開くために頑張るのだが…?
【このキャラデザが"勝ち"2023】
普段、あまり劇場でアニメの予告編を観たくらいでは「ぜひ観よう」とはならないのだが…
『金の国 水の国』に関しては、予告で「あ、これは見るわ」と思った。なんといっても主役2人のキャラデザが、日本アニメでほぼ見たことないものだったからである。
原作漫画も読んでいなかったので、どんな話とかも全然知らなかったわけだが、予告を観た時点で、仮に話が多少つまらなかったとしても、正直もう主役2人のデザインだけである程度「勝ち」だろとまで思わされた(念のため言っておくと"勝ち"というのは売上とかより、作品そのものの価値や新しさに重点を置いた話ね)。
そして公開された映画を観たわけだが、現にこういう脱テンプレ的な造形のキャラクターが、日本アニメで主役を張っているというだけでも、やはり他の作品とはっきり一線を画するフレッシュさを感じられた。
特に新鮮だと感じたのはやはり、ふくよかな体型をした姫・サーラである。まぁ「ふくよか」とは言ったものの、マジで現実の基準で考えればこれくらいの体型は全然「普通」「平均的」の範囲に収まると思うのだが、ともかく日本アニメの主役キャラとしては間違いなく珍しい造形だ。日本アニメ(に限った話では実はないが)で、とりわけ女性キャラの造形が、スリムな美女や美少女のテンプレをできる限り逸脱しないような、かなり狭い範囲に限られがちなことを考えると、サーラの造形は(原作があるとはいえ)特筆すべき大胆なキャラデザと言える。
「アニメのヒロイン」離れした体型のサーラは、おっとりしていて心優しいが、自分の外見に昔からコンプレックスを抱いている。彼女の苦悩の背景には、やはり女性を外見でジャッジして差別する、昔も今も変わらない世の中の歪みがあることも明らかだ。たとえば「最も賢い王子」と「最も美しい姫」の交換…という設定にも、「男は頭脳なのに女は外見なのかよ」という性差別の問題が、それとなく示されていたように思う。そのように抑圧されたサーラが、自分の真の魅力に気づいてくれる誰かと恋に落ち、その優しさと行動力と勇気によって(結果的にではあるが)世界を救うことになる…という物語はエンパワメント的でもあり、大筋こそ古典的ファンタジーである本作に、現代にふさわしい輝きを与えている。
サーラだけでなく、恋の相手となる青年ナランバヤルの、良い意味で平凡さを感じさせる造形もイイ。アニメとかで「平凡な見た目」の立ち位置のキャラのはずが、「美人」「美形」とされるテンプレ的コードから描き分けられてなくないか…?と感じることもよくあるのだが、ナランバヤル君に関してはマジで「平凡な見た目」なんだろうと思わせる説得力が、シンプルな造形にもかかわらずちゃんと生まれている。
そして主役2人のテンプレを逸脱した秀逸なデザインこそが、『金の国 水の国』のファンタジックで童話的な作品世界に、命ある"普通の"人々が暮らしている世界としての、嘘くさくないリアリティと複雑な奥行きをしっかり与えている。その結果、たとえば本作の数少ない(いわゆる)美形なキャラとして「イケメン俳優」な左大臣サラディーンがいるが、彼の存在感も際立っている。貧しい出身で、実は知性的であるにもかかわらず、その美貌ゆえ若干ナメられがちであるなど、なかなか切実な現実感がある奥深いキャラ造形だった。
個人的にフィクションにおける恋愛(特に異性愛)にはあまり興味が湧かないのだが、本作のサーラとナヤンバラルの恋路は素直に応援させられてしまったし、そこは2人のデザインが醸し出す親近感も影響していると思う。美男美女の恋愛は世間にあふれ返りすぎて食傷気味なのだが、「男女どちらも平凡な見た目」の異性愛ロマンスの日本アニメというのは意外と観たことがなかったので、フレッシュに感じた。
「美女と野獣」的な、女性側だけが美人という創作物はすでに沢山あるわけだが、ここでもやはり本作は、サーラが脱テンプレ的な造形の女性キャラであることが効いている。マジョリティであるはずの「男女の恋愛」という枠組みの内部でさえ、実はほとんど描かれてこなかったものが沢山あるのだな…という気づきがあった。いかにキャラクターデザインが作品そのものの「新しさ」をブーストできるかを示す、本作は最良の例のひとつではないだろうか。
冒頭でも触れたが、「普通の人」の平凡な容姿をキャラ造形にうまく反映した本作が、斬新な日本アニメに「なってしまっている」ことから逆説的に、一般的な日本アニメのキャラクターデザインがやはりまだまだ凝り固まっていることを意識してしまったのも確かだ。アニメ『万聖街』の記事↓でも書いたことだが、よりテンプレを打破した「開かれた」キャラデザが、競争力という点でも今後はいっそう重要になっていくと思うので、『金の国 水の国』はその点でも注目されるべきと思う。
【豪華絢爛な美術】
『金の国 水の国』の良さを語る上でキャラデザは筆頭に上がるわけだが、全体的に絵がリッチなので、単純に観ていて楽しいアニメである。特に背景美術に関しては、最近の日本アニメの中でも屈指の豪華絢爛っぷりではないだろうか。アラブ文化を取り入れた、サーラの暮らす「金の国」の街や人々、王宮などの建造物の描写も相当に手が込んでいた。

特にクライマックスで、ある「隠し通路」がド派手に現れてくる場面の迫力はアニメーションならではの圧巻な表現で、舞台となる「金の国」の空間的なスケール感もいっそう壮大なものに感じさせてくれる。気合が入った見せ場に、原作ファンも大満足なことだろう。
ナランバヤルの故郷、中国やモンゴルなどのアジアをモチーフにしたと思われる「水の国」の描写も良い。漫画だと「A国」と「B国」という記号にすぎなかった両国が、精緻な美術表現によって実在感を獲得していて見ごたえがある。

ただ、アニメになって美術の解像度が上がってリアリティが増したことで逆に、水が全然ない砂漠の「金の国」のすぐ隣が、こんなに自然豊かな「水の国」ってこの世界の自然環境どうなってんだよ…とか、やや気になる点が強まったのも確かだ。原作だと導入から思いっきり「童話なのでこのへんは気にしないでね!!」って感じだし、そこまで細かく美術を描き込んでもないので、むしろ気にならないのだが。
それと色々なアジア圏の文化をブレンドしてると思しき水の国はともかく、金の国はわりとそのまんまアラブ文化を完コピしてこのファンタジー童話世界に転用してる感じなので、ガチの現代エンタメの国際水準から言うと、若干「文化の盗用」という言葉がチラつきはじめる瀬戸際になくもないかな…?とか思ったりもした。とはいえ、この程度はまぁよくあるレベルなので、問題になるほどではないと思うし、映画館で観るに値する豪勢な画を楽しませてくれたことに素直に感謝しておきたい。
【意外と今に刺さってるストーリー】
先述したように、両国の設定もかなりフィクショナルだし、全体の「おとぎ話」感は原作でもアニメでも強調されているので、物語は良くも悪くも古典的…なはずなのだが、意外なほど「今」に刺さった物語になってしまっている側面がある。というのも本作、根本的には「資源を巡る戦争を外交で食い止める」話だからだ。
まぁ戦争というのは大抵はなんらかの(物的・人的)資源を巡るものと言えなくもないかもだが、たとえば現在進行中のロシアによるウクライナ侵攻が、本質的にはエネルギー問題を巡る戦争である…という話もよく聞くようになっている。よって大国が武力衝突や帝国主義的な侵略に行き着く前に、登場人物たちが力を合わせて国どうしを融和させようとする…という展開に、なんだか今特有の切迫感が生まれてしまっており、キャラへの応援にも余計に力が入ってしまうというものだ。
そして金の国では「外交」などという営みは、臆病者の腰抜けによる「男らしくない」「王らしくない」所業とされており、外交を試みた王も「腰抜け王」と呼ばれて蔑まれていた。その名前をなぜか親に継がされた現在の王が、"汚名"を克服するために武力を発揮して戦争しようとしている…という、悪しきマッチョイズムに支配された権力の厄介さを巡る物語にもなっている点に着目したい。
そしてそんな王がクライマックスに、マッチョさとはかけ離れた男性であるナランバヤルによって説得される点も面白く感じた。腕も立たないし金もないナランバヤルだが、唯一「口だけは達者」であるという、彼の大きな見せ場にもなっている。ナランバヤルは、金の国では「腰抜け王」と呼ばれていた王が、自分の国では「唯一話のわかるヤツ」だと称賛されていたことを今の王に告げる。価値観というのは場所によってガラッと変わるものだと説くことで、王が囚われている「王らしさ」の概念を相対化してみせるのだ。
最悪な種類のマッチョイズムに取り憑かれ、パワーを誇示したいがためにおかしくなってる権力者が、世界中でヤベー事態を引き起こし続けている今、いっそう本作のクライマックスで伝えられた価値観の転倒や相対化は、平和な世の中を作るために不可欠なステップに思えてくる。旧来的な価値観に囚われない、ナランバヤルの柔軟な考え方や発想、そして彼を惚れさせたサーラの優しさや勇気こそが、この物語の王国にとっても、私たち現実の次世代にとっても、何より大切なものになるはずだ。
【原作も読みました】
というわけでアニメ『金の国 水の国』が全体に楽しめたし、改めて漫画版を読んでみたのだが、けっこう受ける印象が違うな!とも思わされた。率直に言って、より好みなのは漫画版の方である。
情感あふれる方向に舵を切ってるアニメに比べても、原作はけっこう常に何かしらふざけてるような、ドライでユーモラスな空気感が張り巡らされている。みなもと太郎みたいな("プロレス"とかその時代や舞台に絶対ないであろう言葉を急に入れてみたり)細かいギャグもかなり多い。そのことが、事態がシリアスになってきても情緒的・ウェット方向に傾きすぎないような、やや突き放した視点も生んでいて、「なんだかんだ王族の話かよ〜」ともなりかねないこの物語を語る上では、むしろより効果的だと思う。
あと『金の国 水の国』原作、サーラの心情描写がより繊細で丁寧だなと感じた。この一連のコマ↓とか凄くいいんだよね(眉をしかめての"ニコ"が特にいい)。ただこういう微妙かつユーモラスなマンガ表現は、アニメだと再現が難しいというのもわかる。

たとえば映画版を見た時、サーラvs水の国王の飲酒バトルが勃発!というシーンで、突然時間が飛ぶので、「いや普通にバトル見せてほしかったんだが…?」となった。流れ的にもせっかく盛り上げてたし、飲食を愛する彼女の見せ場にもなるし。原作でもあんな感じで時間飛ぶのかな、ひょっとして飲酒シーンゆえに規制かかったとか…?とか観ながら邪推してしまったほどだった。
で、原作『金の国 水の国』を読んだら、そちらでも飲酒バトルはあっさり省略されていたのだが、漫画だともっと「サーラが強すぎてバトルの様子すら描かれない」ギャグなことが明快に感じられた。ここがアニメだと「あれ、バトルは?」となる戸惑いが勝ってしまったんだよね。これはあくまで一例だが、やっぱ漫画とアニメってテンポ感も全然ちがうし、メディアミックスの難しさを改めて感じたり。まぁこの辺は『鬼滅の刃』とか超メジャーどころの漫画のアニメ化にも大いに感じるところなので、本作特有の問題ではまったくないのだが。
…などと色々細かく思ったりもしたが、日本アニメの新しい可能性を感じさせる良作なのは間違いないので、テンプレ的なキャラ造形に若干飽きてきた人にもぜひ観てほしい一作でした。
原作も読もうね!→『金の国 水の国』
大判のスペシャル版もあるらしい。見開きがきれいなので紙ならこっちがいいかも。